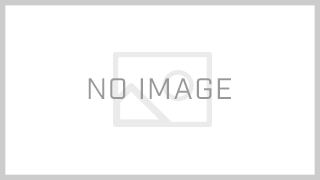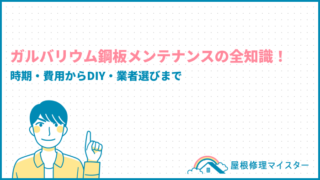当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。
新築やリフォームで屋根材を選ぶ際、ガルバリウム鋼板は人気の選択肢ですが、その本当の寿命やメンテナンスについて、多くの疑問や不安をお持ちではないでしょうか。
結論からお伝えします。ガルバリウム鋼板が実際に屋根として機能する実用耐用年数は25年〜40年が目安です。一方で、税金の計算で使われる「法定耐用年数」は17年であり、これは実際の寿命とは全く異なる数字です。
なぜ、これほど耐用年数に幅があるのでしょうか。
その理由は、使われる製品のグレードや塗料の種類、お住まいの地域環境(沿岸部など)、そして何よりも施工品質とメンテナンスの有無によって、屋根の寿命が大きく変わるためです。つまり、正しい知識を持って製品を選び、信頼できる業者に施工を依頼することが、ガルバリウム鋼板の耐用年数を最大限に引き出す鍵となります。
この記事では、ガルバリウム鋼板の耐用年数について、以下の点を徹底的に解説します。
- 実用耐用年数(25〜40年)と法定耐用年数(17年)の明確な違いと根拠
- 「暑い・うるさい・傷つきやすい」といった後悔を防ぐための完璧な対策
- 寿命を40年以上に延ばすための正しいメンテナンス方法と劣化サインの見極め方
この記事を最後までお読みいただくことで、あなたはガルバリウム鋼板の本当の価値を理解し、ご自宅の状況に合わせた最適な屋根選びができるようになります。屋根リフォームで絶対に失敗しないための知識を身につけ、今後数十年間の安心を手に入れましょう。
関連記事:ガルバリウム鋼板屋根まるわかり!塗装、屋根材、価格、施工方法で選ぶ屋根リフォーム
この記事でわかること
- ガルバリウム鋼板の「実用耐用年数(25〜40年)」と「法定耐用年数(17年)」の具体的な違い
- 耐用年数に「25〜40年」と幅が生まれる3つの理由(製品・環境・施工品質)
- 夏の暑さや雨音で後悔しないための具体的な失敗回避策
- 寿命を最大限に延ばすための正しいメンテナンス方法と劣化のサイン
- 塗装メンテナンスが必要になる最適な時期と費用相場
- SGL鋼板や瓦など、他の屋根材との耐用年数・ライフサイクルコストの比較
- 信頼できる優良な屋根修理業者の見極め方と相見積もりのコツ
- ガルバリウム鋼板の耐用年数は25~40年!2つの年数の違いと根拠
- ガルバリウム鋼板の耐用年数は国税庁の年数と違う?減価償却との関係
- ガルバリウム鋼板の屋根で後悔?よくある失敗例と完璧な対策
- 寿命を最大限に延ばす!ガルバリウム鋼板の正しいメンテナンスと点検
- ガルバリウム鋼板は塗装不要?塗り替えの最適な時期と費用を解説
- ガルバリウム鋼板のメンテナンス費用はいくら?30年間の総額を試算
- ガルバリウムとSGL・瓦!屋根材の耐用年数と費用を徹底比較
- 立地で寿命は変わる?沿岸部や豪雪地帯での耐用年数の違いと対策
- メーカー保証と工事保証は別物!契約前に確認すべき保証内容の全て
- 優良な屋根修理業者の選び方。相見積もりで失敗しないコツ
- 屋根リフォームで使える補助金や火災保険の活用法をわかりやすく解説
ガルバリウム鋼板の耐用年数は25~40年!2つの年数の違いと根拠

ガルバリウム鋼板の屋根を検討する際、最も気になるのが「一体、何年持つの?」という耐用年数ではないでしょうか。実は、ガルバリウム鋼板には2種類の耐用年数が存在します。それは、実際に使用できる期間を示す「実用耐用年数」と、税金の計算で使われる「法定耐用年数」です。
この2つは目的が全く異なるため、年数も大きく違います。実用耐用年数は建材としての本当の寿命を知るための指標、法定耐用年数はあくまで会計上のルールです。この違いを理解することが、後悔しない屋根選びの第一歩です。
この記事では、ガルバリウム鋼板の2つの耐用年数について、その根拠や寿命に影響を与える要因を詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 実際に屋根として使える期間を示す「実用耐用年数」は25年から40年
- 税金の計算で使われる「法定耐用年数」は17年で、実際の寿命とは全く異なる
- なぜ耐用年数に「25年~40年」という幅があるのか、その3つの理由
実際に使用できる期間を示す「実用耐用年数」は25年から40年
ガルバリウム鋼板が屋根材として、雨や風から家を問題なく守り続けられる期間、つまり「実用耐用年数」は、一般的に25年から40年が目安です。この年数は、単なる噂や感覚的なものではありません。
製品を製造しているメーカーが品質を保証する期間や、専門機関が行った耐久性試験の客観的なデータによって、その長さがしっかりと裏付けられています。
なぜこれほど長く性能を維持できるのか、その具体的な根拠を3つのポイントから詳しく見ていきましょう。
メーカーが示す塗膜保証は15年から25年が一般的
ガルバリウム鋼板の耐用年数を考える上で、メーカーが製品に付けている「塗膜保証」がひとつの目安となり、その期間は15年から25年が一般的です。
この塗膜保証は、「最低でもこの期間は、色あせやサビから屋根を守る塗膜の性能を保証します」というメーカーからの約束です。実際の寿命は保証期間よりも長くなることが多いため、この保証期間は耐用年数の下限を知るための信頼できる根拠となります。
例えば、国内大手の鉄鋼メーカーの製品では、より耐久性の高いフッ素樹脂塗装で20年、一般的なポリエステル樹脂塗装でも15年の塗膜保証が付いています。これは、定められた環境下で塗膜に大きな変色や剥がれ、ひび割れなどが生じないことを保証するものです。
長期的な安心を求めるなら、保証期間が長い製品を選ぶことは、メーカーがその製品の耐久性に自信を持っている証拠であり、賢明な選択と言えるでしょう。
保証書で確認すべきポイント
- 保証期間: 何年間の保証か
- 保証対象: 塗膜の色あせ、剥がれ、穴あきなど、何が保証されるか
- 保証の条件: 海岸からの距離や施工方法など、保証が適用されるための条件
- 免責事項: 保証の対象外となるケース(例:自然災害による損傷、飛来物による傷など)
ちなみに、保証には塗膜の性能を保証する「塗膜保証」の他に、サビによる穴あきを保証する「穴あき保証」もあります。こちらはより深刻な劣化に対する保証で、一般的に塗膜保証よりも長い期間が設定されています。
日本金属屋根協会の試験データが示す客観的な耐久性
日本金属屋根協会のような第三者機関が行った試験データも、ガルバリウム鋼板が長期間の使用に耐えることを示す客観的な証拠です。メーカーの発表だけでなく、中立な立場で行われる厳しい耐久性テストの結果は、その高い耐久性への信頼性を大きく高めてくれます。
代表的な試験に「暴露試験」というものがあります。これは、屋外の厳しい環境に建材を長期間設置し、その劣化具合を観察するテストです。この試験において、ガルバリウム鋼板は30年以上経過しても、建材の性能を著しく損なうような大きなサビや性能の低下が見られないという結果が報告されています。
例えば、塩害が厳しい沖縄や、寒暖差と積雪がある北海道といった過酷な環境下でテストが行われ、そのデータが製品開発に活かされています。こうした客観的なデータは、ガルバリウム鋼板が実際の厳しい自然環境に耐えうる性能を持っていることの強力な証明です。数字やデータに基づいた判断をしたい方にとって、こうした第三者機関の試験結果は、製品を選ぶ上で非常に心強い情報となります。
めっき層と塗膜の2層構造が長期的な防食性を実現する仕組み
ガルバリウム鋼板がサビに強く長持ちする秘密は、鋼板を保護する「めっき層」と「塗膜」という二重のバリア構造にあります。この2つの層がそれぞれ異なる役割で鉄の鋼板を守ることで、サビの原因となる雨水や酸素の侵入を長期間にわたって防ぎ続けます。
ガルバリウム鋼板の断面を拡大して見ると、中心の鉄(鋼板)を「アルミニウム・亜鉛・シリコン」で構成されためっき層が覆い、さらにその上を塗装による「塗膜」がコーティングしている構造になっています。
万が一、飛来物などで表面に傷がついて塗膜が剥がれても、その下にあるめっき層が機能します。特に亜鉛には、鉄より先に溶け出してサビの発生と広がりを防ぐ「犠牲防食」という自己治癒のような働きがあります。
この二重の防御機能のおかげで、多少の傷がついてもすぐにサビが全体に広がるのを防ぎ、長期的な美観と防水性を保つことができるのです。
税法上の「法定耐用年数」は17年。実際の寿命とは全く異なる
ガルバリウム鋼板には、もう一つ「法定耐用年数」という年数があります。これは17年と定められていますが、屋根が実際に使える寿命とは全く関係がない数字なので注意が必要です。
なぜなら、法定耐用年数はあくまで税法上のルールで決められた「資産としての価値がゼロになるまでの期間」であり、建材そのものの物理的な耐久性を示しているわけではないからです。
この数字を見て「17年しか持たないの?」と誤解しないよう、その意味と役割を正しく理解しておきましょう。
法定耐用年数は減価償却の計算に使う税法上の数字
法定耐用年数とは、国税庁が定めた、建物などの資産価値を会計ルールに沿って毎年少しずつ減らしていく「減価償却」という処理のために使われる年数のことです。
これは、会社などが所有する建物を資産として考えたときに、年々価値が下がっていく様子を税金の計算に正しく反映させるための会計上のルールであり、屋根の物理的な寿命とは目的が根本的に異なります。
例えば、事務所や工場の屋根をガルバリウム鋼板でリフォームした場合、その工事費用を資産として計上し、17年という期間に分けて経費として処理していくことになります。これはあくまで帳簿上の計算の話です。
ご自宅のリフォームを考えている個人の方には直接関係ないことが多いですが、将来その家を売却したり賃貸に出したりする際には、建物の資産価値を評価する一つの参考指標になることがあります。また、火災保険の保険金額を算出する際に参考にされるケースもあります。
なぜ実際の寿命より短く設定されているのか
法定耐用年数が、実際の寿命よりもかなり短く設定されているのは、物理的な劣化だけでなく、デザインの流行が過ぎ去るなどの経済的な価値の低下も考慮されているためです。
法律では、新しい技術やデザインが登場することによる「陳腐化」も含めて資産価値を計算します。そのため、物理的にはまだ十分使える状態であっても、会計上の価値は早めにゼロになるよう設定されているのです。
例えば、20年前に最新だったスマートフォンが今ではほとんど価値がないように、建物やその設備も時代と共に経済的な価値が下がっていきます。法定耐用年数は、こうした物理的な劣化以外の価値の目減りも反映した数字なのです。
もしあなたが「17年しか持たないの?」と不安に思ったなら、それは全くの誤解です。あくまで税金計算上の都合なのだと安心してください。
主な屋根材の法定耐用年数
| 屋根材の種類 | 法定耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| ガルバリウム鋼板(金属製) | 17年 | 国税庁の「金属造の事務所用」の耐用年数を参照することが多い |
| 瓦(粘土瓦) | 50年 | – |
| スレート | 20年 | 「住宅用のもの」として定められていることが多い |
この表からも、法定耐用年数が必ずしも物理的な頑丈さの順番通りではないことがわかります。
法定耐用年数が過ぎても屋根は問題なく使える
結論として、法定耐用年数の17年を過ぎたからといって、すぐに屋根の修理や葺き替え工事が必要になるわけでは決してありません。
繰り返しになりますが、法定耐用年数は税法上の区切りに過ぎません。適切なメンテナンスをきちんと行っていれば、ガルバリウム鋼板の屋根はその後も10年、20年と、実用耐用年数を迎えるまで長く使い続けることができます。
実際に、20年以上前にガルバリウム鋼板で施工された住宅が、今も全く問題なく大切な家を守り続けている例は日本中に数多くあります。大切なのは、年数の数字に一喜一憂するのではなく、定期的に専門家に見てもらい、屋根の状態を正しく把握することです。
もしあなたの家の屋根が法定耐用年数を超えていても、下記のような深刻な劣化のサインがなければ、慌ててリフォームを検討する必要はありません。
メンテナンスを検討すべき劣化のサイン
- 赤いサビ: めっき層を貫通して鋼板自体がサビている危険なサイン。早急な対応が必要です。
- 白いサビ: めっき層の亜鉛が酸化した状態。初期段階ですが、放置すると赤サビに繋がります。
- 塗膜の膨れ・剥がれ: 塗膜が劣化し、防水機能が低下しているサインです。
- 目立つ傷やへこみ: 傷がめっき層まで達していると、そこからサビが発生しやすくなります。
ガルバリウム鋼板の耐用年数に幅がある3つの理由
ガルバリウム鋼板の耐用年数が「25年~40年」と幅広く言われるのは、主に「製品そのもののグレード」「お住まいの地域の環境」「施工の品質とメンテナンスの有無」という3つの要素が大きく影響するからです。
これら3つの条件は、ご自宅の状況によって一つひとつ異なります。そのため、屋根の実際の寿命も変わり、結果として耐用年数に幅が生まれるのです。ご自身の状況に合わせて考えることで、より正確な耐用年数を予測できます。
理由1:製品のグレード。使われる塗料や鋼板の厚みによる差
屋根材に使われている塗料の種類や、鋼板自体の厚みといった「製品のグレード」によって、ガルバリウム鋼板の耐用年数は大きく変わります。グレードの高い製品ほど、紫外線や雨風に強い高品質な塗料が使われていたり、衝撃に強く頑丈な厚い鋼板が採用されていたりするため、劣化しにくく長持ちするからです。
例えば、塗料には「ポリエステル」「シリコン」「フッ素」「無機」などの種類があります。一般的なポリエステル塗料の製品に比べて、紫外線に非常に強いフッ素塗料や無機塗料を使った製品は、期待できる耐用年数が10年以上長くなることもあります。
また、鋼板の厚みは一般的に0.35mmや0.4mmが使われます。厚い方がへこみへの耐性が高く、遮音性もわずかに向上します。
「初期費用を少しでも抑えたい」なら標準グレードの製品、「とにかく長持ちさせて将来のメンテナンスの手間を減らしたい」なら高グレードの製品、というようにご自身の予算や将来設計に合わせて選ぶことが重要です。
塗料の種類別 特徴比較
| 塗料の種類 | 期待耐用年数(目安) | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ポリエステル | 10~15年 | 標準 | 最も一般的でコストパフォーマンスに優れる |
| シリコン | 15~20年 | やや高め | 汚れがつきにくく、光沢を保ちやすい |
| フッ素 | 20~25年 | 高め | 紫外線に非常に強く、色あせしにくい |
| 無機 | 25年以上 | 高価 | 最も耐久性が高く、超長期的な美観を維持 |
理由2:住んでいる地域の環境条件。塩害や酸性雨の影響
海の近くや工業地帯、豪雪地帯など、お住まいの場所の環境条件も、ガルバリウム鋼板の寿命に大きく影響を与えます。海からの潮風に含まれる塩分(塩害)や、工場からの排煙などがもたらす酸性雨は、屋根の表面を保護している塗膜やめっき層の劣化を早めてしまうからです。
特に海岸から5km以内の塩害地域や、火山灰が降る地域、交通量の多い幹線道路沿いなどでは、一般的な地域に比べて耐用年数が短くなる傾向があります。このような環境では、サビの発生を遅らせるために、こまめに水で洗い流すなどのメンテナンスが推奨されることもあります。
対策として、こうした厳しい環境に建てる場合は、塩害に強い「フッ素樹脂塗装」や、ガルバリウム鋼板のめっき成分を強化して耐久性をさらに高めた次世代の鋼板「SGL(エスジーエル)鋼板」を選ぶことが非常に有効です。
理由3:施工品質と定期的なメンテナンスの有無
どんなに良い製品を使っても、屋根を工事する際の施工品質が悪かったり、その後のメンテナンスを怠ったりすると、ガルバリウム鋼板は本来の寿命を全うできません。
雑な工事は雨漏りの直接的な原因になりますし、定期的な点検や補修をしなければ、最初は小さな劣化だったものが、気づかないうちに建物全体を傷める大きなトラブルに発展してしまうからです。
例えば、屋根材を固定するビスの打ち方が悪く防水パッキンを傷つけてしまったり、屋根材のつなぎ目の防水処理が不十分だったりすると、そこから簡単に雨水が侵入してしまいます。ガルバリウム鋼板の特性を熟知し、丁寧な仕事をしてくれる信頼できる業者に施工してもらうことが、屋根を長持ちさせるための最も重要な第一歩です。
さらに、完成後もご自身でできる範囲のメンテナンス(年に1~2回、雨どいの落ち葉を掃除するなど)を行い、10年~15年を目安に専門家による点検を受けることで、屋根の寿命を最大限に引き出すことができます。
ガルバリウム鋼板の耐用年数は国税庁の年数と違う?減価償却との関係
ガルバリウム鋼板の耐用年数には、税金の計算で使う「法定耐用年数」と、実際に屋根として使える期間を示す「実用耐用年数」の2種類があり、この2つは全くの別物だと考えてください。なぜなら、法定耐用年数は税法上の資産価値を計算するための形式的な年数であるのに対し、実用耐用年数は実際の自然環境で屋根材がどれだけ機能し続けるかという物理的な寿命を示すものであり、それぞれの目的が根本的に異なるためです。
「法定耐用年数」と「実用耐用年数」の違い
| 項目 | 法定耐य年数 | 実用耐用年数(期待耐用年数) |
|---|---|---|
| 年数の目安 | 17年(金属造の住宅用建物) | 25年~40年 |
| 目的 | 税金の計算(減価償却) | 屋根材が実際に機能する期間の目安 |
| 根拠 | 税法(国税庁の定め) | メーカーの保証や試験データ、実績 |
| 参考にする場面 | 事業用建物の確定申告など | 屋根の新築やリフォーム計画 |
例えば、国税庁は金属製の屋根の法定耐用年数を定めていますが、これはあくまで帳簿上の価値を計算するための数字です。これは「減価償却」という会計処理のためにあり、事業用の建物の取得にかかった費用を、法定耐用年数にわたって分割して経費計上する際に使います。そのため、ご自宅が事業に関係ない場合は、この法定耐用年数を気にする必要はほとんどありません。
一方で、メーカーなどが示す実用耐用年数は、実際の暴露試験や実績に基づいた現実的な寿命の目安であり、屋根のリフォーム計画を立てる上で本当に参考にするべきなのはこちらの数字になります。
結論として、ご自宅の屋根のリフォームや新築を考える際は、税務上の法定耐用年数ではなく、実際の性能を示す実用耐用年数を基準に検討することが、後悔のない選択につながります。
ガルバリウム鋼板の屋根で後悔?よくある失敗例と完璧な対策
ガルバリウム鋼板は、耐久性が高くデザイン性にも優れた人気の屋根材です。しかし、その特性を十分に理解せずに選んでしまうと、「こんなはずではなかった」という後悔につながる可能性があります。
後悔する原因の多くは、ガルバリウム鋼板が持つ「金属ならではの弱点」を知らないまま設置してしまうことにあります。しかし、あらかじめ失敗のパターンと対策を知っておけば、後悔を未然に防ぎ、そのメリットを最大限に活かすことが可能です。
ここでは、ガルバリウム鋼板でよくある後悔の事例と、それを解決するための完璧な対策を解説します。
よくある後悔の事例と具体的な対策
【後悔例1】夏の2階が想像以上に暑い
- 原因:金属は熱を伝えやすいため、夏の強い日差しを受けると屋根の表面温度が非常に高くなります。その熱が室内に伝わり、特に2階や屋根裏部屋の温度が上昇しやすくなります。
- 対策:断熱材と屋根材が一体になった製品を選ぶことが最も効果的です。また、太陽光を反射する「遮熱塗料」が塗られたガルバリウム鋼板を選ぶことでも、室温の上昇を大幅に抑えることができます。
【後悔例2】雨音が気になって眠れない
- 原因:ガルバリウム鋼板は薄い金属板であるため、雨粒が屋根に当たると音が響きやすいという特性があります。特に静かな住宅地では、この音がストレスに感じられることがあります。
- 対策:屋根材の下に敷く「下葺き材(ルーフィング)」に、防音性や振動を抑える制振性の高い製品を選ぶことで、気になる雨音を効果的に軽減できます。施工業者に相談し、適切な下葺き材を提案してもらいましょう。
【後悔例3】すぐに傷やへこみができてしまった
- 原因:表面が比較的柔らかいため、強風で飛来物が当たったり、施工中に工具を落としたりすると、傷やへこみがつきやすいという弱点があります。
- 対策:表面に凹凸の加工(エンボス加工など)が施された製品を選ぶと、小さな傷が目立ちにくくなります。そして何よりも、屋根の知識が豊富で、丁寧な作業をしてくれる実績のある業者に依頼することが、設置時の傷やへこみを防ぐ最も確実な方法です。
これらのように、ガルバリウム鋼板の弱点は、適切な製品選びと確かな施工技術によって十分にカバーできます。事前にポイントを押さえておけば、後悔することなく、ガルバリウム鋼板の持つ高い耐久性や美しいデザインといった長所を、長期間にわたって享受できるでしょう。
寿命を最大限に延ばす!ガルバリウム鋼板の正しいメンテナンスと点検
ガルバリウム鋼板の優れた耐久性を最大限に引き出すためには、定期的な点検と正しい知識に基づいたメンテナンスが不可欠です。なぜなら、小さな劣化のサインを見逃さず早期に対応することで、大規模な修理や葺き替え工事を未然に防ぎ、屋根を健康な状態で長く保つことができるからです。
この記事では、ガルバリウム鋼板の寿命を最大限に延ばすための具体的な方法を解説します。
この章のポイント
- 放置すると危険な劣化のサイン
- ご自身で安全にできる日常のチェック項目
- 絶対に避けるべきNGメンテナンス方法
これらのポイントを正しく理解し、大切な住まいを長持ちさせましょう。
放置は危険!耐用年数を著しく縮める劣化症状と点検の重要性
ガルバリウム鋼板の耐用年数を著しく縮める「危険な劣化症状」を事前に知り、定期的に点検することは、住まいの寿命を守る上で非常に重要です。これらの劣化サインを放置してしまうと、サビが内部まで進行し、最終的には雨漏りを引き起こして建物全体の寿命をも脅かす重大な事態に発展する恐れがあるからです。
ここでは、特に注意すべき3つの劣化症状について詳しく見ていきましょう。
もらいサビや傷から発生する「赤サビ」
ガルバリウム鋼板の劣化で最も注意すべきなのは、外部からの傷や金属片の付着によって発生する「赤サビ」です。赤サビは、ガルバリウム鋼板そのものを腐食させて穴を開け、雨漏りの直接的な原因となるからです。
例えば、工事中に発生した金属の切り粉や、近隣の工場・線路から飛来した鉄粉が屋根に付着し、雨水に触れることで発生します。もし屋根の表面に赤い点々やシミのようなものを見つけたら、サビが広範囲に広がる前に、専門家による点検と補修を依頼することが極めて重要です。
塗膜が劣化しめっき層が露出する「白サビ」
屋根の表面に白い斑点のような「白サビ」が現れたら、それは表面の塗膜が劣化しているサインと捉えましょう。白サビは、ガルバリウム鋼板を保護している「めっき層」が紫外線や雨風によって酸化している状態であり、このまま放置すると屋根の防水機能が徐々に失われていくためです。
白サビ自体がすぐに雨漏りを引き起こすわけではありませんが、屋根の保護機能が低下している明確な証拠です。この段階で専門家による塗装メンテナンスを行うことで、より深刻な赤サビの発生を防ぎ、結果的に屋根全体の寿命を延ばすことにつながります。
雨漏りに直結する「コーキングのひび割れや板金の浮き」
屋根材そのものだけでなく、部材のつなぎ目を埋めるコーキングの劣化や、屋根の頂上部を覆う棟板金の浮きにも注意が必要です。なぜなら、これらの部分にひび割れや隙間、浮きが生じると、そこから直接雨水が内部に侵入し、雨漏りに直結するケースが非常に多いからです。
強風によって棟板金が浮いたり、長年の紫外線でコーキングが痩せてひび割れたりすることは珍しくありません。屋根全体を見渡したときに、部材が浮いている、あるいは部材のつなぎ目に明らかな隙間が見える場合は、雨漏りが始まる前に早急に専門業者へ点検を依頼しましょう。
自分でできる!ガルバリウム屋根の日常的なチェック項目
専門業者に点検を依頼する前に、ご自身で安全にできる日常的なチェックを行うことで、屋根の異常を早期に発見できます。庭や2階の窓、ベランダなど、地上から安全に見える範囲で確認するだけでも、劣化の初期サインに気づくことができ、大きなトラブルを未然に防げる可能性があるからです。
ご自宅で簡単に確認できるチェック項目は以下の通りです。
ご自身で確認できるチェックリスト
- 屋根全体の色あせや落ちにくい汚れ
- 日当たりの悪い場所のコケやカビの発生
- 雨樋の詰まりや変形・破損
これらのポイントを定期的に確認する習慣をつけましょう。
色あせや汚れの付着は劣化の初期サイン
屋根全体の色が新築時やリフォーム時と比べて薄くなったり、水をかけても落ちない頑固な汚れが目立ったりするのは、劣化の初期サインです。これらは、太陽の紫外線や雨風によって表面の塗膜が劣化し始めている証拠であり、屋根の防水性が少しずつ低下しつつあることを示しています。
特に、日当たりが良く紫外線の影響を最も受けやすい南側の屋根面は、他の面より劣化が早く進む傾向があります。屋根の色が明らかに白っぽく見える、あるいは以前のようなツヤがなくなっていると感じたら、メンテナンスを検討し始めるタイミングかもしれません。
コケやカビが発生していないか確認する
屋根の表面に緑色のコケや黒っぽいカビが発生していないかを確認することも大切です。コケやカビは水分を長時間保ちやすいため、塗膜の劣化をさらに加速させてしまう原因になります。
特に、日当たりが悪く湿気がたまりやすい北側の屋根面や、樹木が近くにある環境では発生しやすい傾向があります。もし地上から見える範囲でコケやカビを見つけたら、屋根の防水性が落ちてきているサインと考え、専門家への相談を検討しましょう。
雨樋の詰まりや破損は屋根劣化の引き金になる
雨樋に落ち葉や砂、ゴミが詰まっていないか、割れや変形などの破損がないかのチェックも忘れてはいけません。雨樋が詰まると、行き場を失った雨水が屋根から溢れ出し、屋根材の先端部分(軒先)を常に濡れた状態にして腐食させたり、外壁を汚したりする原因となるからです。
大雨が降った際に、雨樋から水が滝のように溢れていないかを確認するのが最も簡単なチェック方法です。また、晴れた日に下から見上げて、雨樋が途中でたわんでいたり、継ぎ目が外れていたりしないかも見てみましょう。
絶対にやってはいけない!寿命を縮めるNGメンテナンス方法
良かれと思ってご自身で行うメンテナンスが、かえってガルバリウム鋼板の寿命を縮めてしまうことがあるため、注意が必要です。ガルバリウム鋼板の表面は、サビを防ぐためのデリケートな塗膜とめっき層で保護されており、誤った方法で清掃するとこれらを傷つけ、劣化を促進させてしまうからです。
例えば、汚れを落とそうと家庭用の高圧洗浄機を強い水圧で屋根に直接噴射すると、塗膜を剥がしてしまうだけでなく、屋根材の隙間から水が浸入し、雨漏りの原因となる危険があります。また、サビを見つけて金属製の硬いブラシでこすり落とそうとすると、保護層に無数の傷がつき、かえってサビの発生範囲を広げてしまうことになりかねません。
屋根の清掃や補修は、専門的な知識と技術が求められる作業です。安全と建物の保護のためにも、必ずガルバリウム鋼板の特性を熟知した専門業者に相談しましょう。
ガルバリウム鋼板は塗装不要?塗り替えの最適な時期と費用を解説
「ガルバリウム鋼板は塗装が不要で長持ちする」と聞き、屋根材の候補に考えている方も多いでしょう。しかし、この「塗装不要」という言葉は、正しく理解しないと将来のメンテナンスで後悔する可能性があります。
結論として、ガルバリウム鋼板も美しい外観と優れた耐久性を長期間維持するためには、いずれ塗り替えメンテナンスが必要になります。なぜなら、「塗装不要」とは「すぐにサビる心配がなく、長期間メンテナンスが楽」という意味合いで使われており、屋根材の表面を保護している塗膜は、紫外線や雨風によって時間と共に必ず劣化するためです。
この記事では、ガルバリウム鋼板の塗装に関する疑問を解決し、後悔しない屋根リフォームを実現するための知識を解説します。
この記事でわかること
- ガルバリウム鋼板に塗装が必要になる本当の理由
- 塗り替え時期を見極めるべき3つの劣化サイン
- 屋根塗装にかかる費用相場とその内訳
- 塗装以外のメンテナンス方法(カバー工法・葺き替え)が適しているケース
これらの情報を知ることで、ご自宅の屋根に最適なメンテナンスを、適切な時期と費用で行えるようになります。
「塗装不要」は誤解?ガルバリウム鋼板に塗装が必要な理由
ガルバリウム鋼板の塗装は、単に見た目をきれいにするだけでなく、屋根材本体をサビから守る保護機能を回復させるために非常に重要です。
表面の塗膜が劣化すると、色あせや汚れが目立つだけでなく、その下にある「めっき層」がむき出しになり、最終的にサビを引き起こす原因になってしまいます。
ガルバリウム鋼板は、鉄の板を「亜鉛・アルミニウム・シリコン」からなる合金のめっき層でコーティングし、サビから守っています。そして、一番外側にある塗装は、この強力なめっき層を紫外線や酸性雨といった外部の刺激から守る「バリア」の役割を果たしているのです。
この塗装というバリア機能が弱まる前に再塗装を行うことで、ガルバリウム鋼板が本来持っている25年以上の長い寿命を最大限に引き出すことができます。つまり、定期的な塗装メンテナンスは、将来的に発生するかもしれない大規模な修理費用を防ぐための、賢い投資と言えるのです。
塗り替え時期の目安は10年から20年。見極めるべき3つのサイン
ガルバリウム鋼板の塗り替えを考え始める時期の目安は、一般的に新築や前回のメンテナンスから10年~20年ですが、ご自身でチェックできる3つの劣化サインを知っておくことが何より大切です。
なぜなら、日当たりの強さや雨量、沿岸部かどうかといったお住まいの環境によって劣化の進み具合は大きく変わるため、年数だけで判断すると最適な塗り替えタイミングを逃してしまう可能性があるからです。
ご自宅の屋根の状態を正しく把握するために、以下の3つのサインに注意してみてください。詳細はこの後で一つずつ解説します。
塗り替えを検討すべき劣化サイン
- サイン1:表面を触ると白い粉がつく「チョーキング現象」
- サイン2:塗膜の膨れや剥がれ
- サイン3:新築時と比べた全体的な色あせや変色
サイン1:表面を触ると白い粉がつく「チョーキング現象」
屋根の表面を指でそっと撫でたときに、チョークの粉のようなものが指についたら、それは塗り替え時期が来たことを知らせる分かりやすいサインです。
この現象は「チョーキング」と呼ばれ、塗料の防水効果が薄れ始めている証拠だからです。チョーキングの正体は、塗料に含まれている顔料が、長年の紫外線や雨風によって分解され、粉状になって表面に現れたものです。
これは劣化の初期サインであり、この段階でメンテナンスを検討することで、より深刻なダメージ(サビの発生など)に進むのを防ぎ、結果的に修理費用を安く抑えることにつながります。ご自宅でも簡単にできるセルフチェックなので、ぜひ一度お試しください。
サイン2:塗膜の膨れや剥がれはサビ発生の危険信号
もし屋根の塗装に水ぶくれのような膨らみや、塗装がパリパリと剥がれている箇所を見つけたら、なるべく早く専門家に見てもらう必要があります。
塗装が膨れたり剥がれたりしている部分は、屋根材を守る「めっき層」がむき出しになっている状態です。この部分が雨水や空気に直接触れるため、サビが発生する一歩手前の非常に危険な状態だからです。
塗膜と鋼板の間に水分が入り込むと、塗膜が風船のようにプクッと膨れることがあります。これを放置すると、やがて塗膜が破れて剥がれ落ち、そこから鋼板を腐食させる「赤サビ」が発生してしまいます。赤サビは一度発生するとどんどん広がり、屋根の寿命を大きく縮める原因となるため、早急な対処が求められます。
サイン3:新築時と比べた全体的な色あせや変色
屋根全体の色がなんとなく薄くなったり、場所によって色が違うまだら模様に見えたりする場合も、メンテナンスを考えるサインの一つです。
色あせは、単に見た目が古びて見えるという問題だけでなく、塗装が紫外線によって劣化し、屋根を守る力が弱まっていることを示しているからです。
新築当時やリフォーム直後の写真があれば、それと見比べてみると色あせの進み具合がよく分かります。特に、一日を通して日当たりが良い南側の屋根面は劣化が早く進むため、北側の屋根面などと色が違って見えることもあります。
この段階であれば、まだ比較的軽い補修で屋根の美しさと保護機能を取り戻すことが可能です。塗装メンテナンスによるビフォーアフターの効果が最も分かりやすく現れるサインとも言えるでしょう。
ガルバリウム鋼板の屋根塗装にかかる費用相場と内訳
一般的な30坪の戸建て住宅の場合、ガルバリウム鋼板の屋根塗装にかかる費用は、およそ40万円から70万円が相場です。
この費用には、塗料そのものの価格だけでなく、安全な作業に不可欠な足場の設置や、塗料の密着性を高めるための高圧洗浄、サビを落とし補修する丁寧な下地処理など、長持ちする塗装を行うための全ての作業費が含まれています。
屋根塗装の費用内訳(30坪の戸建ての場合)
| 項目 | 費用の目安 | 概要 |
|---|---|---|
| 足場代 | 15万円~25万円 | 作業員の安全確保と、丁寧な作業のために設置する仮設足場 |
| 高圧洗浄 | 2万円~4万円 | 汚れや古い塗膜を除去し、新しい塗料の密着を良くする |
| 下地処理・養生 | 3万円~6万円 | サビ落としや補修、塗料が飛ばないように窓などを保護する |
| 塗装費用 | 15万円~30万円 | 塗料代と職人の人件費(シリコンやフッ素など塗料の種類で変動) |
| 合計 | 40万円~70万円 | – |
業者から見積もりを取る際は、上記の項目が含まれているかを確認しましょう。特に、塗料のメーカー名や商品名、何回塗り(通常は下塗り・中塗り・上塗りの3回)か、保証の期間と内容が明記されているかをチェックすることが、後悔しない業者選びの重要なポイントです。
塗装より葺き替えやカバー工法が適しているケースとは
屋根の状態によっては、塗装で補修するよりも、新しい屋根材に交換する「葺き替え」や、今の屋根の上から新しい屋根を被せる「カバー工法」が最適な場合があります。
なぜなら、塗装では直すことができない屋根材自体の深刻なダメージ(穴や広範囲のサビ)があったり、すでに雨漏りが発生していたりする場合、塗装だけでは根本的な解決にならないからです。
例えば、以下のようなケースでは、塗装以外の方法を検討する必要があります。
- 赤サビが広範囲に発生し、鋼板自体がもろくなっている
- 台風などの飛来物で屋根材に穴が開いたり、変形したりしている
- すでに雨漏りしており、屋根の下地(野地板)まで腐食している
また、この機会に「夏の暑さを和らげたい」「雨音を静かにしたい」と考える場合も、断熱材と一体になった屋根材を用いるカバー工法や葺き替えが非常に有効な選択肢となります。
ご自身の家の状況にどの工事が最適か判断するために、以下の比較表を参考にしてください。
屋根のメンテナンス方法 比較表
| 工事方法 | メリット | デメリット | 費用目安(30坪) |
|---|---|---|---|
| 塗装 | 最も安価、工期が短い | 軽微な劣化しか補修できない | 40万円~70万円 |
| カバー工法 | 廃材が少ない、断熱性・遮音性UP | 屋根が重くなる、下地の補修は不可 | 80万円~140万円 |
| 葺き替え | 屋根が新品になる、下地も直せる | 費用が最も高い、工期が長い | 100万円~180万円 |
どの方法が最適か迷った場合は、複数の専門業者に診断を依頼し、それぞれの提案と見積もりを比較検討することをおすすめします。
ガルバリウム鋼板のメンテナンス費用はいくら?30年間の総額を試算
ガルバリウム鋼板の屋根を選ぶ際、初期費用だけでなく、将来かかるメンテナンス費用を含めた「ライフサイクルコスト」で考えることが、賢い選択の鍵を握ります。ここでは、30年間でどれくらいの費用がかかるのか、具体的なシミュレーションを交えて解説します。
ガルバリウム鋼板屋根の30年間ライフサイクルコスト試算(30坪の戸建て住宅を想定)
| 項目 | 費用目安 | 実施時期の目安 |
|---|---|---|
| 初期費用(カバー工法) | 80万円~150万円 | 新築時・リフォーム時 |
| メンテナンス①(屋根塗装) | 40万円~80万円 | 築10年~20年後 |
| メンテナンス②(部分補修など) | 3万円~10万円 | 適宜(点検時に発見) |
| 30年間の合計費用 | 123万円~240万円 | – |
ガルバリウム鋼板のメンテナンス費用は、30年間でおおよそ40万円から100万円が目安です。したがって、屋根材を選ぶ際は初期費用だけでなく、このメンテナンス費用を含めた総額で判断することが非常に重要になります。
なぜなら、たとえ初期費用が安くても、適切なメンテナンスを怠ると、本来の耐用年数よりも早く劣化が進み、結果的に高額な葺き替え工事が必要になるなど、余計な出費につながる可能性があるからです。
具体的なメンテナンスとしては、まず築10年から20年を目安に行う屋根塗装が挙げられます。これには足場の設置費用も含まれ、一般的に40万円から80万円ほどの費用がかかります。また、強風による飛来物での傷や、コーキングの劣化といった部分的な補修は、定期的な点検で早期に発見すれば数万円程度で済みます。
このように、初期費用と将来のメンテナンス費用を合算したライフサイクルコストを把握し、スレートや瓦といった他の屋根材と比較することで、長期的な視点で最もコストパフォーマンスに優れた屋根材を選ぶことができます。
ガルバリウムとSGL・瓦!屋根材の耐用年数と費用を徹底比較
ガルバリウム鋼板が、本当にあなたの家にとって最適な選択肢なのかを判断するには、他の主要な屋根材と耐用年数や費用を比べながら、総合的に考えることが大切です。なぜなら、屋根材選びは初期費用だけでなく、将来のメンテナンスまで含めたトータルコストで考えなければ、後で「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があるからです。
ここでは、ガルバリウム鋼板、次世代のSGL鋼板、そして伝統的な瓦やスレート屋根について、「耐用年数」「初期費用」「メンテナンス」などの項目を一覧表で比較します。この表を見ることで、どの屋根材がご自身の予算や将来設計に合っているか、客観的に判断できます。
主要屋根材の性能・コスト比較一覧
| 屋根材 | 実用耐用年数 | 初期費用(m²単価) | メンテナンス(内容・周期・費用) |
|---|---|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | 25年~40年 | 6,000円~9,000円 | 10年~20年で塗装(30万円~60万円) |
| SGL鋼板 | 30年~50年 | 7,000円~10,000円 | 15年~25年で塗装(30万円~60万円) |
| スレート | 20年~30年 | 5,000円~8,000円 | 10年前後で塗装(30万円~60万円)、20年~30年でカバー工法や葺き替え |
| 陶器瓦 | 50年以上 | 9,000円~15,000円 | 漆喰補修(10年~20年)、瓦自体は半永久的で塗装不要 |
この比較表を参考に、ご自身の優先順位(初期コスト、耐久性、デザイン性など)を明確にし、長期的な視点で最適な屋根材を選びましょう。
立地で寿命は変わる?沿岸部や豪雪地帯での耐用年数の違いと対策
ガルバリウム鋼板の寿命は、お住まいの地域環境によって大きく左右され、特に塩害を受けやすい沿岸部や雪深い豪雪地帯では短くなる可能性があります。なぜなら、潮風に含まれる塩分や、積雪・凍結による物理的なダメージが、サビや塗膜の劣化を通常より早く進行させてしまうからです。
例えば、沿岸部では潮風の塩分が屋根に付着し、サビの発生を早めます。また、豪雪地帯では雪の重みや、凍結と融解の繰り返しが屋根表面を傷つけ、劣化を促進します。
しかし、立地条件に合わせて適切な対策を講じることで、ガルバリウム鋼板の耐用年数を最大限に引き出すことが可能です。ここでは、地域ごとの主なリスクと、屋根を長持ちさせるための具体的な対策を解説します。
立地環境別のリスクと対策
| 環境要因 | 主なリスク | 推奨される対策 |
|---|---|---|
| 沿岸部(塩害) | ・めっき層の腐食(白錆・赤錆)の促進 | ・より錆に強いSGL鋼板を選ぶ ・定期的に屋根を水で洗い流す ・塩害に強い塗料でメンテナンスする |
| 豪雪地帯 | ・積雪の重みによる屋根の変形 ・落雪による屋根表面の傷 ・凍害による塗膜の劣化 |
・雪止め金具を設置する ・積雪の重さに耐えられる設計にする ・滑りやすい塗料を選ぶ |
| 都市部・工業地帯 | ・酸性雨による塗膜の劣化 ・砂塵や排気ガスなどの付着 |
・汚れが付きにくい塗料を選ぶ ・定期的な点検と清掃を行う |
このように、お住まいの環境を正しく理解し、それに適した製品選びや施工、メンテナンスを行うことが、大切な家の屋根を長持ちさせる秘訣です。特に塩害が懸念される地域では、より耐食性に優れたSGL鋼板の採用や、海岸からの距離に応じて水洗いなどのメンテナンス頻度を増やすことが有効です。
メーカー保証と工事保証は別物!契約前に確認すべき保証内容の全て
屋根の保証には、製品の不具合を対象とする「メーカー保証」と、工事の不備が原因で起こる不具合を対象とする「工事保証」の2種類があります。この2つの保証は役割が全く異なり、両方の内容を契約前に正しく理解しておくことが、長期的な安心のために極めて重要です。
なぜなら、万が一雨漏りなどのトラブルが起きた際に、その原因が製品の欠陥なのか、それとも施工不良なのかによって、適用される保証が変わってくるからです。
この記事では、2つの保証の具体的な違いと、契約前に保証書で必ず確認すべきポイントを、誰にでも分かりやすく解説します。
メーカー保証と工事保証の主な違い
| 項目 | メーカー保証(製品保証) | 工事保証(施工保証) |
|---|---|---|
| 保証する人 | 屋根材メーカー | 工事を担当した業者 |
| 保証の対象 | 製品自体の不具合(サビ、塗膜の剥がれなど) | 工事の不備による不具合(施工不良による雨漏りなど) |
| 保証の期間 | 15年~25年(製品による) | 1年~10年(業者による) |
| 注意点 | 施工不良が原因の不具合は対象外 | 製品自体の欠陥は対象外。保証がない業者もいる。 |
メーカー保証:製品の品質を約束するもの
メーカー保証とは、ガルバリウム鋼板などの屋根材を製造したメーカーが、その「製品自体の品質」を保証する制度です。これは、製品の品質証明書のような役割を果たします。
具体的には、「塗膜が著しく色褪せたり剥がれたりしないこと」や「サビによる穴あきが発生しないこと」などを、一定期間保証するものです。例えば、塗膜の保証期間は15年~25年、穴あき保証は25年などが一般的です。
ただし、この保証はあくまで製品の製造上の欠陥が対象です。したがって、業者の施工ミスが原因で発生した雨漏りや、台風などの自然災害による破損、メンテナンス不足による劣化などは保証の対象外となる点に注意が必要です。
工事保証:施工技術に責任を持つ証
工事保証とは、屋根の修理やリフォームを行った施工業者が、自社の「工事の品質」を保証する制度です。これは、業者の技術力と責任感を示す重要な証となります。
例えば、「屋根材の固定方法に不備があって雨漏りが発生した」「板金の納め方が悪く、強風で剥がれてしまった」といった、工事が原因の不具合が保証の対象です。
しかし、この工事保証の内容は業者によって千差万別です。保証期間が10年と長期にわたる信頼できる業者もいれば、わずか1年、あるいは保証制度自体を設けていない業者も存在します。どんなに高品質な屋根材を使っても、工事がずさんでは意味がありません。そのため、業者を選ぶ際には、この工事保証の内容が非常に重要な判断材料となります。
契約前に絶対確認!保証書で見るべき3つのポイント
口約束はトラブルの元です。後で「言った、言わない」という問題を避けるため、契約前には必ず「保証書」を書面で提示してもらい、以下の3点を自分の目で確認してください。
保証書で確認すべき重要項目
- 保証期間: メーカー保証と工事保証、それぞれが「何年間」有効なのかを正確に把握します。期間の起算日も確認しておくとより安心です。
- 保証の対象範囲: 「どのような症状」が保証されるのかを具体的に確認します。「サビ」「塗膜の剥がれ」「雨漏り」など、具体的な文言で記載されているかチェックしましょう。「一式」などの曖昧な表現は要注意です。
- 免責事項: 「どのような場合に保証が適用されないのか」という条件を確認します。一般的には、自然災害(台風、地震、雹など)や、施主側の不注意による損傷、経年劣化などが記載されています。この内容を理解しておくことで、無用なトラブルを防げます。
これらの内容に少しでも疑問や不安を感じたら、契約書にサインする前に、業者が納得できるまで説明を求めることが大切です。2つの保証内容をしっかり確認することが、今後数十年にわたる住まいの安心を守ることに直結します。
優良な屋根修理業者の選び方。相見積もりで失敗しないコツ
ガルバリウム鋼板の優れた性能を最大限に引き出すためには、技術力が高く誠実な業者を選ぶことが不可欠です。そのための最も確実な方法が、複数の業者から見積もりを取って比較する「相見積もり」です。
なぜなら、1社だけの見積もりでは、提示された価格や工事内容が本当に適正なのかを客観的に判断できません。気づかないうちに損をしたり、知識の乏しい業者や悪質な業者を選んでしまったりするリスクが高まるからです。
相見積もりを成功させるには、ただ複数社から見積もりを集めるだけでなく、その中身を正しく比較することが重要になります。優良業者を見極めるために、以下の3つのポイントを重点的にチェックしましょう。
優良業者を見極める3つのチェックポイント
- 詳細な見積書か確認する: 「屋根工事一式」といった大雑把な記載ではなく、使用する材料(ガルバリウム鋼板のメーカー名・製品名など)、単価、数量、工事内容(板金工事、下地処理、足場設置など)が細かく書かれているかを確認します。詳細な見積書は、工事に対する誠実さの表れです。
- 工事後の保証内容が明確か確認する: メーカーが製品の品質を保証する「製品保証」と、施工業者が工事の品質を保証する「工事保証」の2種類があります。保証期間はもちろん、どのような場合に保証が適用されるのか、保証の範囲を書面で明確に提示してくれる業者を選びましょう。
- 担当者の対応が誠実か見極める: あなたの質問に対し、専門用語を多用せず、分かりやすく丁寧に答えてくれるかは重要な判断基準です。また、メリットだけでなく、ガルバリウム鋼板のデメリットや工事のリスクについても正直に説明し、あなたの家の状況に合わせた最適な提案をしてくれる担当者は信頼できます。
これらのポイントを複数の業者で比較検討することで、単に価格が安いだけでなく、長期的に安心して付き合える、技術力と信頼性の高い優良な業者を見抜くことができます。
屋根リフォームで使える補助金や火災保険の活用法をわかりやすく解説
屋根リフォームにかかる費用は、国や自治体の補助金、または火災保険を上手に活用することで、自己負担を大きく減らせる可能性があります。なぜなら、住宅の性能向上や安全確保を目的とした公的な支援制度や、自然災害による損害を補償する保険制度が用意されているからです。
この章では、屋根リフォームの費用負担を賢く軽減するための具体的な方法について、以下の点を中心に解説します。
この章で解説するポイント
- 国や自治体が提供する補助金・助成金制度
- 火災保険が適用されるケースと申請方法
- 制度を利用する上での重要な注意点
具体的には、断熱性能の高い屋根材へのリフォームで国から補助金が出たり、お住まいの市区町村が独自にリフォーム助成金制度を設けていたりします。ただし、これらの補助金は予算や受付期間が決まっている場合が多いため、工事を計画する段階で必ずお住まいの自治体のホームページを確認するか、リフォーム業者に相談することが不可欠です。
また、台風や大雪といった自然災害で屋根が壊れた場合には、火災保険の「風災補償」や「雪災補償」などを利用して修理費用をまかなえることがあります。ここで最も重要なのは、保険が適用されるのはあくまで自然災害による突発的な損害であり、経年劣化による雨漏りや故障は対象外となる点です。保険を申請する際は、被害の原因が自然災害であることを写真などで明確に証明する必要があります。
このように、利用できる制度を正しく理解し、事前に条件を確認・準備することで、屋根リフォームの経済的負担を大幅に軽くすることが可能になります。

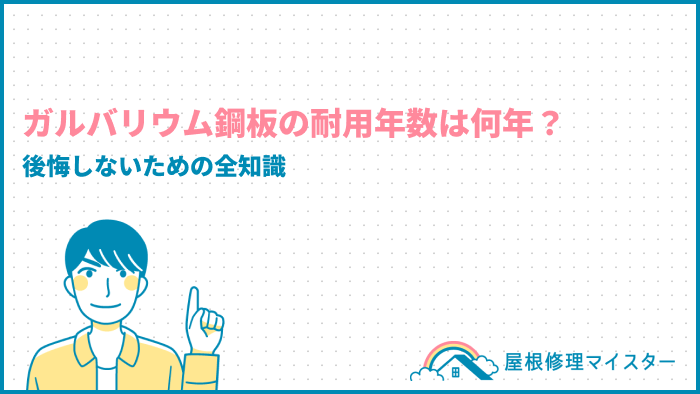


 街の屋根やさん埼玉上尾店
街の屋根やさん埼玉上尾店 
 雨漏り修理110番
雨漏り修理110番 
 雨漏り屋根修理DEPO
雨漏り屋根修理DEPO