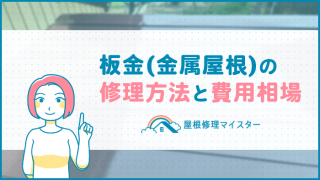当サイトは、複数の会社と協力して情報を提供しており、商品・サービスの申込みの際など、各企業から支払いを受けることがあります。掲載の順番には報酬等が考慮されています。
棟板金の交換費用は1mあたり7,000円~12,000円、一般的な住宅なら総額10万円~30万円が相場です。総額には足場代など工事に必要な費用が全て含まれています。
| 1mあたりの平均相場 | 7,000~12,000円 |
| 30坪住宅の平均相場 | 10万~30万円 |
費用は棟の長さや下地の劣化状況によって大きく変動するため、相場を知らないまま依頼すると、不必要な工事で数十万円も損をしてしまう危険性があるからです。
例えば、軽い釘の浮き程度なら数万円の補修で済む一方、下地まで腐食が進んでいると、交換費用が40万円以上になるケースも少なくありません。
この記事では、棟板金交換の費用について、誰にでもわかるように徹底解説します。この記事を読めば、あなたの家の適正な費用相場がわかり、高額請求してくる悪質業者から身を守る知識が身につきます。
修理と交換の正しい判断基準や、火災保険を使って自己負担を0円に近づける方法まで具体的に紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 棟板金交換の費用相場(m単価・総額・足場代込み)
- 「交換」と数万円で済む「部分修理」の判断基準
- 費用が高くなる3つの要因(棟の長さ・下地劣化・足場)
- 火災保険や助成金を使って費用を安くする方法
- 高額請求を避けるための見積もりチェックポイント
- 信頼できる優良業者の見分け方
棟板金の修理・交換の費用相場について
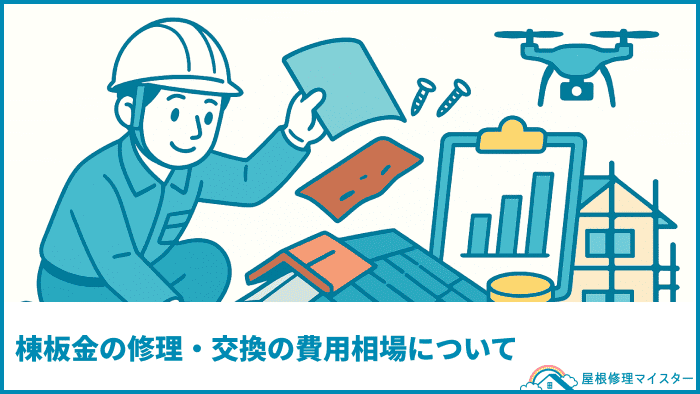
棟板金の修理・交換費用は、工事の内容や家の状況によって大きく変わるため、複数の費用パターンを知ることが大切です。一式費用だけでなく、単価や追加費用、家の状態別の総額を知ることで、ご自宅に近い費用感を正確に把握し、高すぎる見積もりを避けられます。
棟板金交換・修理にかかる費用
棟板金の修理には主に「棟板金交換」「貫板交換」「釘の打ち直し」の3つがあります。
さらに、屋根上に上る作業のため、足場の設置が費用になる関係上、足場代としておよそ10~20万円がプラスされます。
| 工事内容 | 総額 |
|---|---|
| 棟板金交換 | 5万~20万円 |
| 貫板交換 | 5万~15万円 |
| 釘の打ち直し | 5万~20万円 |
棟板金の修理が以上の3つが主な作業となり、劣化症状によってこれらの作業が必要になってきます。
例えば、一般的な2階建て住宅(棟の長さ15m程度)の場合、足場を組んで棟板金と下地の貫板をすべて交換すると、総額で25万~50万円前後になることが多いです。
内訳としては、棟板金交換の工事費が5万~20万円、下地である「貫板交換」が5万~15万円、足場設置費用が15万円ほどかかります。もし劣化が軽微で、足場が不要な平屋などの場合は、30万円程度で済むこともあります。
| 例:棟板金の工事費用 | 25万~50万円 |
|---|---|
| 棟板金交換 | 5~20万円 |
| 貫板交換 | 5万~15万円 |
| 足場代費用1 | 15万円~ |
注意点として、見積もりで「一式」と書かれている場合でも、必ず「棟板金本体費」「貫板交換費」「撤去処分費」「コーキング処理費」「諸経費」などの内訳を確認することが重要です。内訳が不透明な見積もりは、高額請求のリスクがありますので注意しましょう。
棟板金交換の1m単価の目安
棟板金の交換費用は、1mあたり7,000円から12,000円が単価の目安です。この単価には材料費と工事費が含まれており、ご自宅の棟の長さを知ることで、おおよその工事費用を自分で計算できます。
| 棟板金の1m当たりの交換費用相場 | 7,000~12,000円 |
例えば、棟の長さが合計で20mある家の場合、「棟の全長(20m)× 単価(円/m)」で計算します。単価7,000円/mなら14万円、12,000円/mなら24万円が、棟板金交換自体の費用目安となります。
使用する板金の素材(現在はサビに強いガルバリウム鋼板が一般的)や、下地の貫板を木材から腐食しにくい樹脂製に変える場合などで、単価は変動します。
ご自宅の棟の長さがわからない場合は、建物の図面(立面図)を確認するか、業者に無料点検を依頼して正確に測定してもらうのが確実です。危険ですので、ご自身で屋根に登って測るのは絶対にやめましょう。
足場代など追加費用も含めた合計額
棟板金交換の総額は、工事費のほかに足場代として15万円~が追加でかかるのが一般的です。2階建て以上の住宅では、作業員の安全確保と作業品質の向上のために足場の設置が法律で義務付けられており、省略できない費用だからです。
足場代は家の外周や高さによって費用が変わり、1平方メートルあたり700円から1,000円が単価の目安です。
| 一般的な住宅の足場代(約30坪) | 15万円~ |
| 1㎡あたりの費用目安 | 700~1,000円/㎡ |
足場代は高額ですが、せっかく足場を組むなら、同時に屋根塗装や外壁塗装、雨樋の修理など、他の高所作業もまとめて行うと効率的です。将来的にかかる足場代を一度で済ませることができ、トータルコストを大幅に節約できます。
雨漏りや飛散で復旧範囲が広い場合の費用
すでに雨漏りが発生している、または棟板金が飛散して下地が腐食している場合、復旧費用は50万円以上になる可能性があります。これは、棟板金と貫板の交換だけでなく、その下の防水シート(ルーフィング)や、屋根の下地である野地板(のじいた)の補修・交換といった追加工事が必要になるからです。
つまり、修理規模が、棟板金のみの修理ではなく”屋根全体の修理”になってしまうケースです。
棟板金が剥がれた箇所から雨水が侵入し、下地の木材(貫板や野地板)が腐ってしまうと、単に板金を交換するだけでは雨漏りは止まりません。
屋根修理に関する費用相場については、以下の記事で詳しく解説しています。ご心配の方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
関連記事:屋根修理の費用相場はいくら?修理方法・屋根材・劣化状況別に解説
棟板金交換の見積もり費用の内訳
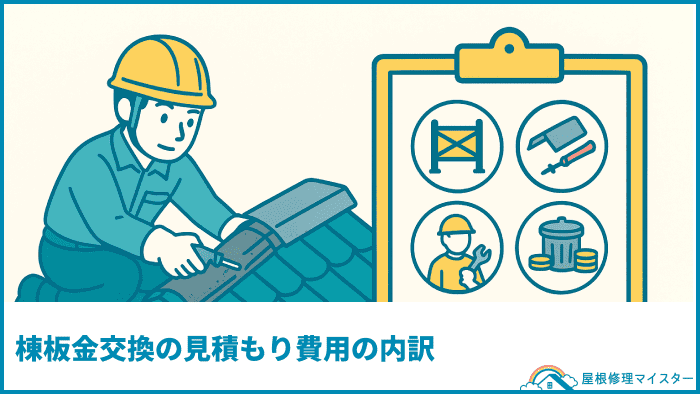
棟板金交換の費用は、何にいくらかかっているのかを正しく理解することが、適正価格で契約するための最も重要なポイントです。この点を把握しないまま契約すると、業者の言い値で進んでしまい、不要な高額工事を支払うリスクが高まります。
この記事では、安心して棟板金交換を依頼するために、以下の点を詳しく解説していきます。
見積書で必ず確認する費用項目
見積書を受け取ったら、まず「工事一式」とまとめられていないかを確認しましょう。以下の内容が細かく記載されているかをしっかり確認しましょう。
- 棟板金本体
- 貫板交換費用
- 足場代
- 撤去処分費
信頼できる見積書には、以下のような項目が単価と数量と共に明記されています。
良い見積書の記載例
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|
| 棟板金 本体(ガルバリウム鋼板) | 7,000円/m | 15m | 105,000円 |
| 貫板 交換(樹脂製) | 3,000円/m | 15m | 45,000円 |
| 既存棟板金・貫板 撤去処分費 | 2,000円/m | 15m | 30,000円 |
| シーリング処理 | 800円/m | 15m | 12,000円 |
| 足場設置・解体(飛散防止ネット込) | 800円/㎡ | 180㎡ | 144,000円 |
| 諸経費 | – | 一式 | 33,600円 |
このように、計算の根拠が明確であれば、どの作業にいくらかかるのかが一目瞭然です。もし「一式」とだけ書かれていたら、「この一式には何が含まれていますか?」と必ず具体的に質問し、内訳を明らかにしてもらいましょう。
棟板金交換にかかる費用の意味
棟板金の交換費用が高くなるのは、単純な板金交換だけでは済まず、工事の範囲が広くなったり、追加の作業が必要になったりする場合です。ご自宅の屋根の劣化状況や家の構造によって必要な作業が変わるため、その要因を知っておくことで、見積もり金額の妥当性を判断できます。
金額が変動する主な理由は、以下の4つです。
棟板金の長さ
屋根の棟が長かったり、複数あったりする家は、交換する棟板金の材料費と作業の手間が増えるため費用が高くなります。
費用は基本的に「材料や工事の単価 × 長さや数量」で計算されるため、施工する量が増えれば、総額も比例して上がることが理由です。
- 一般的な戸建て住宅の棟の長さ:10m〜15m程度
例えば、棟板金交換の単価が1mあたり8,000円の場合、10mなら8万円ですが、ご自宅の棟が20mあれば材料費も人件費も約2倍の16万円になります。また、複数の面が合わさる寄棟(よせむね)屋根のように、棟が複数ある形状の家は、その分費用が高くなる傾向があります。
下地の貫板が腐っていて交換が必要な場合
棟板金の下にある木材の「貫板」が雨水で腐っている場合、その交換費用が追加されるため総額が高くなります。
腐った貫板の上に新しい棟板金を被せても、釘やビスがしっかりと固定されず、数年でまた浮いたり飛んだりしてしまうため、下地の交換は安全上必須の作業だからです。
- 貫板交換の費用相場:1mあたり2,000円〜4,000円程度
例えば、棟の長さが15mなら、3万円〜6万円程度の追加費用が発生する可能性があります。もし貫板を交換しないまま工事を進めると、数年でまた修理が必要になり、結果的にもっと費用がかさむリスクがあるため、下地の状態を正しく判断し、必要であれば交換することが重要です。
最近では、従来の木材だけでなく、腐りにくい樹脂製の貫板という選択肢もあります。樹脂製は少し高価ですが、水分を吸わず耐久性が非常に高いため、長期的な安心を得たい方におすすめです。
雨漏りや飛散で復旧範囲が広い場合
すでに雨漏りが発生していたり、棟板金が広範囲にわたって飛んでしまったりしている場合は、見えない部分の補修も必要になり、費用が高額になります。被害が屋根の下地材である防水シート(ルーフィング)や野地板(のじいた)にまで及んでいると、その部分を直すための追加作業が発生するためです。
被害状況による費用イメージ
| 被害状況 | 追加工事の可能性 | 総額の目安(足場代込) |
|---|---|---|
| 軽い浮き・釘抜けのみ | 貫板交換のみ | 20万円~35万円 |
| 雨漏りが発生している | 貫板交換+防水シート補修+野地板交換 | 40万円~60万円以上 |
雨漏りがある場合、防水シートの補修で数万円、下地の野地板の張り替えが必要になると数万円から十数万円の追加費用がかかることもあります。
被害を放置するリスクは非常に大きく、「最初は20万円で済んだはずが、放置した結果、下地が広範囲に腐ってしまい、屋根全体のリフォームで150万円以上かかった」というケースも少なくありません。被害の拡大を防ぐためにも、早期の対応が重要です。
足場設置が必要で費用が上がる場合
棟板金の交換工事では、作業員の安全確保と作業品質を維持するために、原則として足場の設置が必要です。その費用が総額に加算されるため、全体の金額が大きく上がります。屋根の上は高所で大変危険なため、法律でも安全対策が求められており、安全かつ丁寧な作業を行うためには足場が不可欠なのです。
| 項目 | 30坪あたり | 1㎡あたり |
| 足場設置費用の相場 | 15万~20万円 | 700~1,000円 |
「足場なしで安くやります」という業者は、安全を軽視している可能性が高く、手抜き工事につながる危険性があります。
せっかく高額な足場を組むのであれば、この機会に屋根塗装や外壁塗装、雨樋の修理など、他の高所作業もまとめて行うと、将来的に別々に足場を組むよりトータルの費用を抑えられます。長期的なメンテナンス計画も視野に入れて検討するのが賢い方法です。
関連記事:屋根修理の足場費用はいくら必要?工事費用を抑える方法を伝授!
屋根の棟板金交換の工事の流れと工期
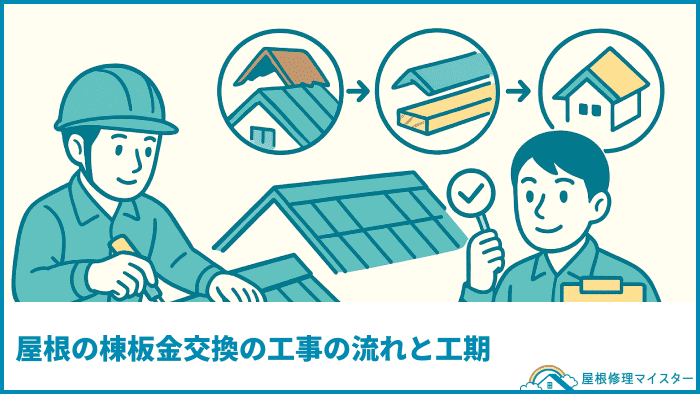
棟板金の交換工事は、古いものを取り外して新しいものに取り替えるシンプルな流れで進みます。足場を設置する関係上、おおよそ2日は要するケースが多いです。
| 棟板金の交換・修理にかかる日数 | 1日~2日程度 |
工事は「既存の棟板金を剥がす」「下地である貫板を交換する」「新しい棟板金を取り付ける」「つなぎ目をコーキングで防水処理する」という明確な手順で行われるため、効率的に作業を進めることができます。
棟板金交換の基本的な手順
一連の作業は、屋根の大きさや形状にもよりますが、多くの場合1日以内に完了します。
| 1.既存の棟板金・貫板の撤去 | 既存の棟板金と貫板を外し撤去する。 |
| 2.下地の確認。貫板の交換 | 下地の劣化度合いを確認し、必要であれば貫板の交換を行う。 |
| 3.面戸の取り付け | 棟内部の雨水等の進入を防ぐ面戸を取り付け。 |
| 4.棟板金の取り付け | 貫板と棟板金を取り付けしっかり固定します。 |
棟板金交換の緊急度の目安
棟板金の交換が必要かどうかは、劣化のサインを見ることで、ご自身でもある程度判断できます。症状によって雨漏りや板金が飛ばされるリスクの高さが全く異なるため、緊急度を正しく見極めることが、大きな被害を防ぎ、無駄な修理費用を抑える第一歩です。
ご自宅の屋根がどの状態に近いか、以下のサインを確認してみましょう。
今すぐ専門業者に相談すべき危険なサイン
以下の症状が1つでも見られる場合、放置すると雨漏りや板金の飛散といった重大なトラブルにつながる可能性が非常に高いため、直ちに専門業者による点検と修理が必要です。
| 症状 | 解説 |
|---|---|
| 板金の大きな浮き・めくれ | 強風で板金が剥がされ、飛散する危険性がある。 |
| 強風時の異音 | 「バタバタ」「ガタガタ」という音がする場合、板金に緩みが発生している。 |
| 板金の剥がれ・飛散 | すでに一部が無くなっている状態は、雨水が直接浸入する危機的な状況。 |
| 下地木材(貫板)の腐食 | 板金を固定する力が弱まり、少しの風でも飛散しやすい。 |
| 雨漏りの発生 | すでに建物内部へ被害が及んでいるため、早急な対処が不可欠。 |
計画的なメンテナンスを検討するサイン
今すぐ交換が必要なわけではありませんが、劣化が進行しているサインです。放置すると危険な状態に移行するため、早めに専門業者に相談し、メンテナンス計画を立てることをおすすめします。
| 症状 | 解説 |
|---|---|
| 釘の軽い浮き | 釘が少しだけ抜けてきている初期症状。 |
| コーキングのひび割れ・剥がれ | 板金のつなぎ目から雨水が浸入しやすくなる。 |
| 表面の軽いサビ | サビが進行すると穴が開き、雨漏りの原因になる。 |
| 色あせや塗膜の剥がれ | 防水性能が低下しているサイン。 |
もし危険なサインが一つでも当てはまる場合は、被害が拡大する前にすぐに専門業者へ点検を依頼してください。様子見のサインであっても、いずれは修理が必要になるため、早めの相談で修理費用を抑えることにつながります。
火災保険や助成金で棟板金交換の費用負担を下げる方法
棟板金の交換費用は、火災保険や自治体の助成金、工事の工夫を組み合わせることで、自己負担を大きく減らせる可能性があります。台風などの自然災害による破損は火災保険の対象となる場合があるほか、自治体の制度や工事の進め方次第で総額を賢く抑えられるためです。
ここでは、費用負担を軽減するための3つの具体的な方法を解説します。
火災保険の「風災補償」を活用する
台風や強風、竜巻といった自然災害によって棟板金が破損した場合、ご加入の火災保険に付帯する「風災補aturation」が適用できる可能性があります。
風災補償が適用される主なケース
- 台風で棟板金が飛んでしまった
- 強風で棟板金がめくれた、浮いてしまった
- 飛来物によって棟板金が破損した
一方で、経年劣化によるサビや釘の緩み、施工不良が原因の場合は対象外です。まずは保険証券を確認し、保険会社や代理店に連絡して、補償の対象となるか相談してみましょう。
ただし、「保険金が使える」と勧誘し、高額な手数料を請求する悪質な業者には注意が必要です。保険申請は契約者ご自身で行うのが基本であり、信頼できる修理業者は申請に必要な書類(被害状況の写真や見積書)の作成をサポートしてくれます。
自治体の助成金・補助金制度を調べる
お住まいの市区町村によっては、住宅リフォームに関する助成金や補助金制度を設けている場合があります。制度の有無や条件は自治体によって異なりますが、費用の一部が補助される可能性があるため、工事契約前に確認することをおすすめします。
確認方法は、お住まいの自治体のホームページで「住宅リフォーム 助成金」や「屋根改修 補助金」といったキーワードで検索するのが最も簡単です。ただし、多くの場合、予算の上限や申請期間が定められているため、早めに情報を集めることが重要です。
足場が必要な工事を同時に行い、総コストを削減する
棟板金の交換工事では、安全確保のために足場の設置が必須となることが多く、この足場代が費用総額の大きな割合を占めます。一度設置した足場を有効活用し、他のメンテナンスも同時に行うことで、将来的なコストを大幅に削減できます。
同時施工がおすすめな工事の例
- 屋根の塗装
- 外壁の塗装や補修
- 雨樋の交換・修理
- アンテナの交換
これらの工事を将来別々に行うと、その都度足場代(15万~20万円程度)が発生してしまいます。棟板金交換のタイミングでまとめてしまえば、足場代は1回分で済み、長期的に見て大きな節約につながるのです。業者に見積もりを依頼する際に、他に気になる箇所がないか相談してみると良いでしょう。
これらの方法を活用できるか判断するには、まず屋根の専門家による正確な状況把握が不可欠です。ご自身の状況でどの方法が最適か、信頼できる業者に相談しながら検討を進めましょう。
関連記事:屋根修理を火災保険で全額カバーしたい人必見!自己負担を減らす3つの方法とは?
棟板金が浮いてると言われた時の注意点と悪徳業者の見分け方
突然、訪問してきた業者から「お宅の屋根の棟板金が浮いていますよ。このままだと雨漏りします」と指摘されても、その場で契約するのは絶対に避けてください。親切を装って不安を煽り、不要な高額工事を契約させようとする悪質な業者が存在するからです。
冷静に判断し、大切なお住まいと資産を守るために、悪質な業者の手口と信頼できる優良業者の特徴を知っておきましょう。
悪質業者の典型的な手口
悪質な業者は、あなたの不安や知識のなさに付け込んできます。以下のようなトークには特に注意が必要です。
注意すべき営業トークの例
- 「通りがかりに見たら、屋根が大変なことになっていました」と突然訪問してくる
- 「今すぐ工事しないと、次の台風で飛んで大変なことになりますよ」と過度に不安を煽る
- 「今日中に契約してくれるなら、キャンペーンで半額にします」と即決を迫る
- 「火災保険を使えば自己負担0円で直せます」と、保険申請の代行や安易な適用をうたう
- 詳細な見積もりを出さず、「一式〇〇万円」と大雑把な金額だけ提示する
これらの言葉は、冷静な判断をさせずに契約を結ばせるための常套句です。もしこのようなセールスを受けたら、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
信頼できる優良業者の見分け方
一方で、優良な業者は顧客の立場に立って、丁寧で誠実な対応を心がけています。業者選びの際は、以下のポイントを確認してください。
優良業者を見分けるチェックポイント
- 写真やドローンで現状を報告: 口頭だけでなく、屋根に登らず確認できる写真や動画で、劣化箇所を具体的に示してくれます。
- 詳細な見積書を提示: 「棟板金交換工事一式」ではなく、「板金代」「貫板(下地)代」「撤去処分費」「足場代」など、項目ごとに単価と数量が明記された詳細な見積書を提出します。
- 質問に的確に回答: 工事内容や費用について質問した際に、専門用語を避け、分かりやすく丁寧に説明してくれます。
- 契約を急かさない: 「一度ご家族で相談してみてください」「他社さんの見積もりも取って比較してください」と、考える時間を与えてくれます。
- 建設業許可や資格を保有: 会社のウェブサイトなどで、建設業許可の有無や、建築板金技能士などの資格保有者が在籍しているかを確認できます。
突然の指摘に慌てる必要はありません。まずは複数の信頼できる専門業者に無料点検を依頼し、相見積もりを取ることが、適正価格で質の高い工事を行うための最も確実な方法です。
関連記事:屋根修理の悪徳業者を見抜く!騙されないための7つのポイントと対策
棟板金をホームセンターで直すのは危険かと安全な確認方法
棟板金の浮きや釘抜けが気になっても、ご自身で屋根に登って修理するのは絶対にやめてください。最も安全で確実な方法は、専門業者が行う無料点検を利用して、屋根の状態を正確に把握することです。
なぜなら、高所での作業は転落という命に関わる危険が伴うだけでなく、専門知識がないまま修理することで、かえって雨漏りを悪化させてしまうケースが非常に多いからです。
例えば、ホームセンターで材料を揃えても、慣れない屋根の上では足元が不安定で、転落事故につながる恐れがあります。また、良かれと思ってコーキング材を塗った場所が、実は水の通り道(雨仕舞)で、出口を塞がれた雨水が別の場所から室内に侵入する原因になることも少なくありません。
一方で、信頼できる専門業者は、お客様を危険な目に遭わせることなく屋根の状態を確認できます。ドローンや高所カメラを使い、お客様は地上にいながら、ご自宅の屋根の様子を写真や映像で隅々まで確認することが可能です。劣化箇所を客観的な証拠と共に示してくれるため、修理が必要な理由も明確に理解できます。
ただし、無料点検を利用する際は、悪質な業者に注意が必要です。安心して相談できる業者を選ぶために、以下の点を確認しましょう。
信頼できる無料点検業者の見分け方
- 点検後に必ず写真や映像を見せて、具体的に説明してくれる
- その場で契約を急かしたり、しつこく勧誘したりしない
- 見積もりの内訳が明確で、質問に丁寧に答えてくれる
まずは安全な方法で現状を正しく知ることが、適切な修理への第一歩です。

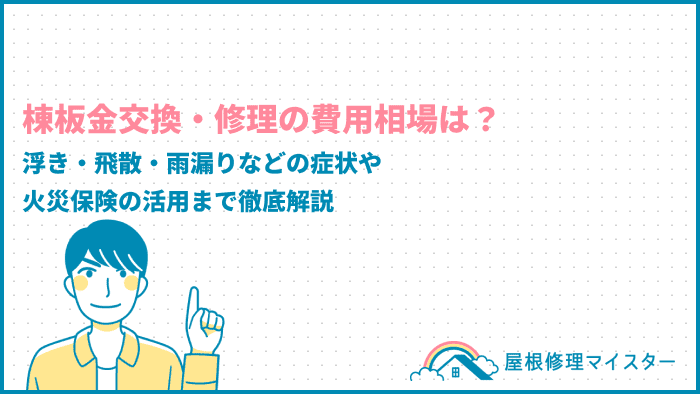
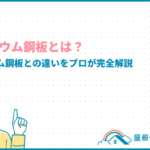
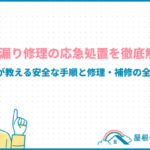
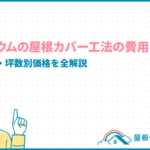
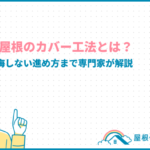

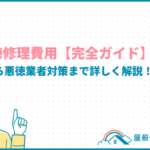
 街の屋根やさん埼玉上尾店
街の屋根やさん埼玉上尾店 
 雨漏り修理110番
雨漏り修理110番 
 雨漏り屋根修理DEPO
雨漏り屋根修理DEPO